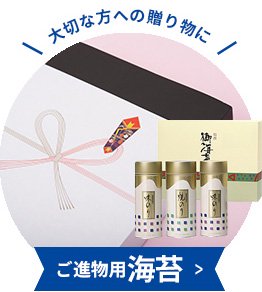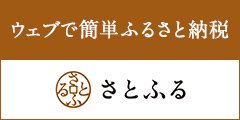大昔から続く海苔の歴史
海苔というのは歴史が古く日本に海苔という言葉がまだなかった頃から食べられていました。文章として残されている1番古い歴史がある記述は陸奥国風土記という地方の風物のことを記してある書物の中の日本武尊の歌です。 万葉の歌や常陸地方と出雲地方の風土記にも海苔についての記述がされています。仏教が飛鳥時代に普及するのに伴って殺生が良くないこととされたので海藻が食材として食べられるようになったのです。 西暦702年の現在は海苔の日と定められている2月6日に施行された税制の一種である大宝律令にも紫菜という名前で海藻の貢納品の1つとして定められています。平安時代には五位以上の地位のある貴族にしか支給されない最も貴重な品として取り扱われていて庶民には縁がないものとなっていたという歴史があるのです。 昔から日本人と深く食生活に関わっている海苔はアマノリのことを意味します。新鮮なアマノリは甘い香りがして食べると甘味がかすかに感じられるのです。そして昔は紫菜と書いてノリと読み、神仙菜と書いてアマノリと読んでいました。平安時代末期頃からは甘海苔と書かれる様になり江戸時代になってから海苔と書かれる様になったという歴史があります。 紫菜は中国から伝わった言葉でノリと読んでいたのが、やがてムラサキノリと読まれるようになりました。古代中国では神仙とは不老長寿の神様のことなので神仙菜は不老長寿の効果がある薬草と考えられていたと推測されます。
海苔の豆知識一覧へ戻る